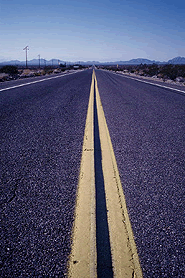ギター専門情報サイト・楽器検索 | Jギター J-Guitar.comは国内最大級のギター情報サイトです
- HOME
- 楽器を探す条件を選んで絞り込みながら探す
- こだわり検索詳細条件を設定して一発で探す
- かんたん検索ギターや楽器をワンクリックで探す
- カテゴリ一覧ギターや楽器の種類から探す
- ブランド一覧楽器メーカーやブランド名から探す
- 楽器店一覧ギターショップ・楽器店を探す
- 新着楽器新着楽器を登録日ごとに表示
- プレミアムセレクションビンテージ&プレミアム
- SALE!公式セール・店舗セール・タイムセール
- 値下げ商品!セール以外でもお買得楽器が満載!
- 閲覧履歴
- ブックマーク
- かんたん買取査定全国の楽器店が無料で査定!
- ギターテクニック完全無料の人気ギター講座
- ENGLISH
- 閉じる
ギターテクニック-Guitar Technique-
ギター初心者からベテランまでが楽しめる無料ギター講座。初心者向けの『ギター★はじめの一歩【動画編】』、中級/上級者のための『音楽理論やアドリブ、ソロギターやスライドギター』など、充実した内容の動画と譜面を掲載!もっともっとギターにハマろう!

僕は、民主党支持者でもなんでもない。もちろん、自民党支持者などではない(ジャクソン・ブラウンがよくアンコールで歌ってくれるスティーヴ・ヴァン・ザントの名曲「アイ・アム・ア・パトリオット」の歌詞を真似てみた)。とはいうものの、のっけから脱線気味で申し訳ないが、民主党が目指す高速道路無料化には全面的に賛成したい。「渋滞を激化させる」とか「エコに逆行」といった批判は、まったくの筋違いだし、もともと道路はそれぞれの国=国民の財産として、あるいはインフラの基盤として、無料であるべきものなのだ。
アメリカの道を走っていて通行料をとられることは、ほとんどない。例外的に長いトンネルや橋が有料になってはいるものの、たとえばサンフランシスコのゴールデン・ゲート・ブリッジでは、上り車線(ソウサリート方面から街の中心部に向かう路線)の車しか徴収されない。それも、3ドルだ。マンハッタンのトンネルも然り。すべて理にかなっている。日本の高速道路にあたるインターステイト・ハイウエイ(州間道路)には馬鹿げたテーマパーク的サービスエリアなどないが、困ったことはない。出入り口が多いので、飲んだり食べたりしたくなったら、気が向いたところで街に出ればいいのだ。
まあ、そんなわけで早く無料化が実現したらいいのにと思いつつ(脱線ばかりで申し訳ないが、民主党には飲食店などの全面禁煙も実現してほしい)、この背景には、ハイウェイを、高速道路を意味する言葉だと誤解させられつづけてきたという事情があるのではないかと、やや無理な理論展開であることを承知のうえで、結論づけた。
振り返ってみると、ビートルズやストーンズのシングルをお年玉で買っていたころからもう45年近くの歳月が流れた。そして40年ほど前からは、文化ということを意識してロックを聴くようになり、さらにそれから数年たったころには、歌われている言葉の意味やその向こう側にあるものを理解したいと強く思うようになっていた。
とはいうものの、「好きだ、嫌いだ」、あるいは「別れた、悲しい」といった次元のものを別にすれば、この島国で暮らす僕らには理解できないものがほとんどだった。なかでも大きな壁となっていたのが「ハイウェイ」という言葉だった。
たとえば、ブルースの名曲で、デレク&ザ・ドミノスの『レイラ』にも収められていた「キー・トゥ・ザ・ハイウェイ」。あるいはボブ・ディランの、ロックの時代の大きな転換点を飾った「追憶のハイウェイ61」。イーグルスの「テイク・イット・トゥ・ザ・リミット」には今回のコラムのタイトルに使わせてもらった印象的なフレーズが何度も出てくる。「俺はハイウェイ41を走るバスのなかで生まれた」という刺激的な歌詞で主人公が自己紹介するオールマン・ブラザーズ・バンドの「ランブリン・マン」も忘れられない。
使命を終え、今はもうまったく使われていない道。オクラホマ州のどこかであったと思う。これがもともとの街道であり、時代の変化に応じて、右側に新しい道がつくられていったようだ。
とりわけぐっさりとやられたのは、ジェイムス・テイラーの、旅をテーマにした名盤『マッド・スライド・スリム』のB面6曲目、「またハイウェイに立って」という象徴的な言葉が何度も繰り返される「ハイウェイ・ソング」だ。「今夜もひとり/ホリデイ・インの見慣れた壁に囲まれて」という歌詞もあり、なんとなくぞくぞくしながら聴いたものだった。
以前にも紹介したが、ロバート・ジョンソンが1930年代半ばに残した「ミー・アンド・デ・デヴィル・ブルース」には、究極のフレーズがある。「俺が死んだらハイウェイの脇に埋めてくれ/この邪悪な魂がいつでもまたバスに飛び乗れるように」。
ミシシッピ州クラークデイル郊外の農道。ブルースの道についてはあらためて詳しく書くが、こういう場所でロバート・ジョンソンは悪魔に魂を売ったのかもしれない。
西海岸に沿って走る101号線、アリゾナの大地を貫いて走る州間道路40号線、幻の道=ルート66、ブルースを南から北に運んだ61号線、ミシシッピの郡道、カナダとの国境の南側を走る2号線。歌を聴きながら、あるいは風のなかから歌を聴き取りながらさまざまな道を走るうちに、僕はようやく、若いころに心をつかまれた「ハイウェイ」という言葉の意味が理解できたような気がする。と、書いているうちに、また旅心がうずいてきた。困ったものだ。
最後にひとつ。歌や小説のなかで「ブルー・ハイウェイ」という言葉に遭遇したら、さらに注意が必要だ。これを「青く輝く高速道路」などと訳してしまったら、とんでもないことになる。ブルー・ハイウェイとは通し番号もつけられていない道のことらしい。思いっきり深読みすれば「裏街道」といったところではないだろうか。
コラムで紹介した音楽
デレク&ザ・ドミノス
いとしのレイラ
ロバート・ジョンソンをはじめとする偉大なブルースマンたちへの敬愛の念と実らぬ愛への苦しい想いを、25歳のクラプトンが自身のブルースへと昇華させた作品。ジミ・ヘンドリックスの名曲「リトル・ウィング」の優れたカバーも収められている。(大友)
ボブ・ディラン
追憶のハイウェイ61
「フォークからロック」への転換点という表現は馬鹿げたものだと思うのだが、いずれにしてもその、20世紀音楽の最重要期を象徴する歴史的名盤。オープニングに据えられているのは、多くの人の人生を変えた、あるいは決定づけた「ライク・ア・ローリング・ストーン」だ。(大友)
イーグルス
呪われた夜
ドン・フェルダーを新たなギター・ヒーローの地位へと押し上げたタイトル曲をはじめ多くのヒットを生み出したイーグルスの通算4作目。本文中の「テイク・イット・トゥ・ザ・リミット」ではベースのランディ・マイズナーがリード・ヴォーカルを担当している。(大友)
オールマン・ブラザーズ・バンド
ブラザース&シスターズ
デュアン・オールマンが事故死したあと、キーボーディストのチャック・リヴェールを迎えることで態勢を建て直した彼らが「絆」をテーマにつくり上げたアルバム。「ランブリン・マン」はディッキー・ベッツの作品で、デュアンのフォロワーだったレス・デューデックもギターで参加している。(大友)
ジェイムス・テイラー
マッド・スライド・スリム
70年代初頭のシンガー・ソングライター・ブームを牽引したジェイムス・テイラーの代表作。キャロル・キングの作品で全米1位まで上昇した「君のともだち」も収められている。(大友)
ロバート・ジョンソン
キング・オブ・ザ・デルタ・ブルース・シンガーズ [Best of]
ロバート・ジョンソンは、ミシシッピを中心に南部諸州を旅しながら29の録音作品を残し、1938年、27歳の若さで謎の死を遂げた。これは、1961年にコロムビアがはじめて彼の作品を正式にアルバム化したもの。クラプトンは16歳でこのアルバムを聴き、強い衝撃を受けたという。(大友)
楽器を探す
ギターテクニック 記事一覧
- 初心者向け
- ┠【ギター選びから!】ゼロから始めるギター
- ┠ギターはじめの一歩【動画編】
- ┗ウクレレを弾こう
- 初/中級者向け
- ┠ギター好きも楽しめる、ソロ・ウクレレ講座
- ┠ルーツへ帰ろう!!<復刻版>
- ┠ルーツへ帰ろう!!【動画編】
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?<復刻版>
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?【動画編】
- ┠ドレミでアドリブ 簡単攻略法【動画編】
- ┠アコギで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┠エレキで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┗イマドキ ロックギター入門【動画編】
- 中級者/上級者向け
- ┠ジャジーなソロアコギ
- ┠アコギ定番フレーズをサクッとトライ!
- ┠ワンランクアップのためのアコギ術
- ┠ワンランクアップのためのエレキ術
- ┠ソロギターをもっと楽しく!アコギ・アレンジ講座
- ┠高みへ挑戦!トミー・エマニュエル・スタイル
- ┠セッションマスターへの道【動画編】
- ┠アイリッシュギターを嗜もう<復刻版>
- ┠アイリッシュギターを嗜もう【動画編】
- ┠アコースティック ソロギター道場【動画編】
- ┠ソロアコギ・アレンジ講座【動画編】
- ┠ジャジーなギターで差をつけよう!【動画編】
- ┠アコギで弾こう!ブルースギター【動画編】
- ┠のりのりFUNKYリズムギター【動画編】
- ┠カントリー&ロカビリー【動画編】
- ┠いまどき ソロアコギ【動画編】
- ┗アドリブ入門【動画編】
- レビュー & 豆知識
- ┠試奏の流儀
- ┠ギターよもやま話
- ┠動画でレビュー!! J-Guitar試奏室
- ┗アコギ エレアコ化計画
- コラム
- ┠ソロ・ウクレレ、いかがでしょう?
- ┗大友博の音楽旅コラム
< アーカイブ >
- 初心者向け
- ┗ギターはじめの一歩
- 初心者/中級者向け
- ┠フレットで覚える音楽の仕組み
- ┠スライドギター天国
- ┗アコースティック ソロギター道場
ギターテクニック 記事一覧
- 初心者向け
- ┠【ギター選びから!】ゼロから始めるギター
- ┠ギターはじめの一歩【動画編】
- ┗ウクレレを弾こう
- 初/中級者向け
- ┠ギター好きも楽しめる、ソロ・ウクレレ講座
- ┠ルーツへ帰ろう!!<復刻版>
- ┠ルーツへ帰ろう!!【動画編】
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?<復刻版>
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?【動画編】
- ┠ドレミでアドリブ 簡単攻略法【動画編】
- ┠アコギで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┠エレキで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┗イマドキ ロックギター入門【動画編】
- 中級者/上級者向け
- ┠ジャジーなソロアコギ
- ┠アコギ定番フレーズをサクッとトライ!
- ┠ワンランクアップのためのアコギ術
- ┠ワンランクアップのためのエレキ術
- ┠ソロギターをもっと楽しく!アコギ・アレンジ講座
- ┠高みへ挑戦!トミー・エマニュエル・スタイル
- ┠セッションマスターへの道【動画編】
- ┠アイリッシュギターを嗜もう<復刻版>
- ┠アイリッシュギターを嗜もう【動画編】
- ┠アコースティック ソロギター道場【動画編】
- ┠ソロアコギ・アレンジ講座【動画編】
- ┠ジャジーなギターで差をつけよう!【動画編】
- ┠アコギで弾こう!ブルースギター【動画編】
- ┠のりのりFUNKYリズムギター【動画編】
- ┠カントリー&ロカビリー【動画編】
- ┠いまどき ソロアコギ【動画編】
- ┗アドリブ入門【動画編】
- レビュー & 豆知識
- ┠試奏の流儀
- ┠ギターよもやま話
- ┠動画でレビュー!! J-Guitar試奏室
- ┗アコギ エレアコ化計画
- コラム
- ┠ソロ・ウクレレ、いかがでしょう?
- ┗大友博の音楽旅コラム
< アーカイブ >
- 初心者向け
- ┗ギターはじめの一歩
- 初心者/中級者向け
- ┠フレットで覚える音楽の仕組み
- ┠スライドギター天国
- ┗アコースティック ソロギター道場