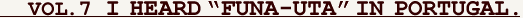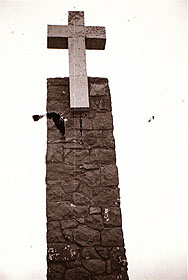ギター専門情報サイト・楽器検索 | Jギター J-Guitar.comは国内最大級のギター情報サイトです
- HOME
- Find Instruments and Buy
- Bookmark
- Browsing History
- Easy Buyback Assessment
- Premium Selection
- Category List
- Brand List
- Easy Search
- Musical Instrument Store List
- Guitar Technique
 JAPANESE
JAPANESE
- HOME
- Find Instruments and Buy条件を選んで絞り込みながら探す
- Advanced Search詳細条件を設定して一発で探す
- Easy Searchギターや楽器をワンクリックで探す
- Category Listギターや楽器の種類から探す
- Brand List楽器メーカーやブランド名から探す
- Musical Instrument Store Listギターショップ・楽器店を探す
- New Arrivals新着楽器を登録日ごとに表示
- Premium Selectionビンテージ&プレミアム
- SALE!公式セール・店舗セール・タイムセール
- 値下げ商品!セール以外でもお買得楽器が満載!
- Browsing History
- Bookmark
- Easy Buyback Assessment全国の楽器店が無料で査定!
- Guitar Technique完全無料の人気ギター講座
 JAPANESE
JAPANESE- 閉じる
- HOME
- Guitar Technique
- 大友博の音楽旅コラム LONESOME HIGHWAY VOL.7 I HEARD “FUNA-UTA” IN PORTUGAL. by J-Guitar.com
ギターテクニック-Guitar Technique-
ギター初心者からベテランまでが楽しめる無料ギター講座。初心者向けの『ギター★はじめの一歩【動画編】』、中級/上級者のための『音楽理論やアドリブ、ソロギターやスライドギター』など、充実した内容の動画と譜面を掲載!もっともっとギターにハマろう!

しばらく前から、理由はよくわからないのだが、アルヴォ・ペルトの「カントゥス・イン・メモリアム・ベンジャミン・ブリテン」が頭のなかで鳴りつづけている。イ短調の下降スケールが延々と繰り返されるあの曲が。なぜなのだろう?僕のなかに少なからずある欧州的なものへの憧れがまたまた頭をもたげてきたのだろうか。

リスボンの市電。線路が敷かれているとはいえ、器用に路地を走り抜けていく運転手のテクニックには拍手を送りたくなる。なお、今回のコラムで紹介した写真はすべて、ミノックスという超小型フィルム(サイズは小指の爪ほど)で撮影したものだ。
アルヴォ・ペルトは旧ソ連邦エストニア出身の作曲家だ。クラシックや現代音楽はまったくの門外漢なのだが、たしか、80年代の半ば、ECMのサンプラーCDでギドン・クレメール版を聴いて、深く、深く引き込まれてしまったのだった。2001年にはリトアニアかどこかの管弦楽団が東京芸術劇場でペルトの作品を演奏するという情報をキャッチして、池袋まで足を運んでいるはずだ。その年の秋にニューヨークで起きた同時多発テロをテーマにした映画『ファーレンハイト9/11』で、監督のマイケル・ムーアが、恐ろしいほど適切なアプローチでこの曲を使っていたことも忘れられない。ちなみに紹介しておくと、あの映画を閉めくくっていたのは、ニール・ヤングの「ロッキン・イン・ザ・フリー・ワールド」だった。
同じ年、01年の春から初夏にかけて、ポルトガルを二度訪れている。当時何度か仕事をいただいていた会社から、ちょっと趣向の変わった、というか、やや視点を変えた音楽番組を企画したいという話があり、お手伝いすることになった。そして、あれこれとミーティングや放送局、関係者との交渉をつづけていくうち、八代亜紀さんがファドで「舟歌」を歌うという企画が成立したのだった。もちろん、本場リスボンに行っていただいて、ということだ。
リスボンの市電。線路が敷かれているとはいえ、器用に路地を走り抜けていく運転手のテクニックには拍手を送りたくなる。なお、今回のコラムで紹介した写真はすべて、ミノックスという超小型フィルム(サイズは小指の爪ほど)で撮影したものだ。
そんな次第で、ロケハンと撮影がそれぞれ1週間という、かなりの時間をポルトガルで過ごすことになった。鉄砲やキリスト教など、さまざまな面で日本の社会や文化に影響を与えた欧州大陸最西端の国を訪れるのはそれがはじめてのこと。貴重な旅となったのだが、ロケハンと撮影のあいだに、邦訳が出たばかりだったミラン・クンデラの『無知』を読んで僕は、かなり意義深いシンクロニシティ的な体験をしている。チェコスロバキアの出身で、70年代以降はパリに拠点を置き、現在はフランス語での創作活動をつづけている偉大な文学者はその作品の第二章冒頭でこんなことを書いていた。
ギリシャ語で、NOSTOSは帰還、ALGOSは苦しみを意味する。この二語が合成されたものがフランス語の単語NOSTALGIEであり、大多数のヨーロッパ人がこれを起源とする言葉を使っている。満たされぬ欲望によって引き起こされる苦しみといった意味の言葉だ。しかしポルトガルには、その系統の単語がなく、異なった言葉を使う。それがSAUDADE=サウダージ(集英社刊、西永良成氏訳より)。そしてじつは、そのサウダージという概念こそが、ファドの重要なキーワードだったのだ。
あらためて紹介しておくと、ポルトガルは欧州大陸の南西部から突き出したイベリア半島の西側に位置する、大西洋に沿って南北に細長く伸びる国。こうした地理的条件が、15世紀から17世紀にかけての大航海時代、その先駆者/主導者としての地位をポルトガルに与えたわけだ。
旧市街のアルファマにはネコがたくさんいる。写真からはもちろん伝わらないと思うが、あたりには塩をふっただけのイワシを炭で焼くいい匂いが漂っていて、ネコにとっては天国のような場所なのかもしれない。
首都のリスボンは、その細長い国土の下から三分の一あたりに位置する人口60万ほどの街。ヴェンダース95年の作品『リスボン物語』でも描かれていたとおり(宮崎駿監督の『魔女の宅急便』も、上空から眺めたこの街の景観を参考にしているらしい)、細かく入り組んだ路地や急な坂が多く、長い歴史を感じさせる石畳の道や、そういった道を器用に走り抜けていく市電が強く印象に残っている。とりわけ旧市街アルファマ地区の、迷路のような街並は今も記憶から消えることがない。
滞在中はリスボンにベースを置き、学園都市のコインブラや海辺のリゾート地ナザレなどにも足を伸ばした。70年代の初頭、檀一雄が暮らしたサンタクルスという漁村では、毎日のように顔をみせていた小さなレストランで、大好きだったという赤ワインDAO(発音はダンに近い)をたっぷりと飲んだりもしたものだ。海に面した公園には「落日を 拾ひに行かん 海の果て」という句碑も建てられていた。旅の作家らしい美しい句だ。
事前に調べていたことではあるが、ポルトガルの人たちはシーフードをよく食べる。たとえば炭で焼いただけのイワシとか、タラの干物を使ったオムレツとか、どれも懐かしささえ感じさせる旨さだった。そういった食べ物と、DAOに代表されるしっかりとしたテイストのポルトガル・ワインがよくあう。海に面した細長い土地なのだから、海の恵みを大切にするのは当然といえば当然のことだが、ファドはこの食文化とも深い部分でつながっているものだった。
大航海時代の栄光が象徴するとおり、古くから、ポルトガルの男たちの多くは海に生活の糧を求めてきた。しかし、昔も今も、海での仕事は危険と背中あわせのもの。海辺の街には、愛する人を海で失い、深い喪失感とともに生きるたくさんの女たちがいる。
サウダージは、彼女たちの想いや気持ちとつながる言葉であり、一概にはいえないが、ポルトガル特有の音楽ファドは、そういったもろもろの状況や感情を背景に生まれたものなのだと思う。
八代亜紀さんの「舟歌」は、アルファマのファド酒場で収録した。ファドの伝統を守りながら意欲的に新しい分野への挑戦もつづけているミージアの共演を得ることもでき、彼女の歌を聴きにきた人たちを前に八代さんは、ミージア専属のミュージシャンをバックに、見事に「舟歌」のファド・ヴァージョンを歌い上げた。クラシックや現代音楽同様、演歌も門外漢だが、これもまた、いつまでも忘れることができない、貴重で特別な体験となった。
ガット弦のギターとポーチュギーズ・ギターをバックに女性シンガーが歌うというのが、ファドの一般的なスタイルだ。ポルトガル固有のこのギターは、通常のギターよりもやや小さくて、復弦の12弦。マンドリンと12弦ギターを合体させた感じ、といったらいいだろうか。熊手のようなヘッドが不思議な存在感を主張している。けっこうな値段だったこともあり、「日本では弦が買えないはず」などと勝手に決め込んで購入を断念したのだが、こうやって原稿を書いているうちに後悔の念がわいてきた。これもまた、サウダージといえるのだろうか。
コラムで紹介した音楽
James D. Best, Arvo Part
Best Of Arvo Part [Import] [from UK]
本文中に紹介した「カントゥス・イン・メモリアム・ベンジャミン・ブリテン」を含むアルヴォ・ペルトのベスト・セレクション。ブリテンはペルトが高く評価していた英国人音楽家。76年に他界しているのだが、その翌年、ペルトはこの作品を発表している。(大友)
Original Soundtrack
Music Inspired by Fahrenheit 9/11 [Soundtrack] [Import] [from US]
世界を震撼させたあの事件に、マイケル・ムーアらしい視点と手法で迫った問題作のオリジナル・サウンドトラック。ブッシュの演説に「ロッキン・イン・ザ・フリー・ワールド」のイントロが重なってくるエンディングも秀逸。(大友)
ミラン クンデラ
無知 (単行本)
「存在の耐えられない軽さ」など多くの名著を残してきたクンデラが00年に発表した作品で、仏語で書いたものとしてはこれが3作目となる。本文でも紹介したノスタルジーをめぐる考察が通奏音のように流れていて、クンデラ版「オデュッセイア」と呼んでいいかもしれない。(大友)
ミージア
リチュアル
アマリア・ロドリゲスらによって築き上げられたファドの伝統やスタイルを守りながらも、意欲的に新しい要素を取り込み、個性的な創作活動を展開している女性アーティスト。これは、個人的なリスボンの思い出ともつながる01年の作品。(大友)
アマリア・ロドリゲス
アマリア・ロドリゲス
ファドの可能性を広げ、多くの名曲を残した音楽家としてだけでなく、ポルトガルの民主化にも大きく貢献した国民的英雄。彼女が眠る墓地には今も多くの人が訪れる。これは代表曲「暗いはしけ」などを含むベスト・セレクション。(大友)
監督:ヴィム・ヴェンダース
リスボン物語 (ユニバーサル・セレクション2008年第5弾) 【初回生産限定】 [DVD]
もっとも尊敬する監督/映像作家、ヴェンダースが94年に発表した作品。リスボン市の要請を受けて制作されたものだそうで、路地や市電など街の景観を生かしながら、いかにも彼らしい物語が展開されている。(大友)
Find Instruments and Buy
ギターテクニック 記事一覧
- 初心者向け
- ┠【ギター選びから!】ゼロから始めるギター
- ┠ギターはじめの一歩【動画編】
- ┗ウクレレを弾こう
- 初/中級者向け
- ┠ギター好きも楽しめる、ソロ・ウクレレ講座
- ┠ルーツへ帰ろう!!<復刻版>
- ┠ルーツへ帰ろう!!【動画編】
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?<復刻版>
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?【動画編】
- ┠ドレミでアドリブ 簡単攻略法【動画編】
- ┠アコギで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┠エレキで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┗イマドキ ロックギター入門【動画編】
- 中級者/上級者向け
- ┠ジャジーなソロアコギ
- ┠アコギ定番フレーズをサクッとトライ!
- ┠ワンランクアップのためのアコギ術
- ┠ワンランクアップのためのエレキ術
- ┠ソロギターをもっと楽しく!アコギ・アレンジ講座
- ┠高みへ挑戦!トミー・エマニュエル・スタイル
- ┠セッションマスターへの道【動画編】
- ┠アイリッシュギターを嗜もう<復刻版>
- ┠アイリッシュギターを嗜もう【動画編】
- ┠アコースティック ソロギター道場【動画編】
- ┠ソロアコギ・アレンジ講座【動画編】
- ┠ジャジーなギターで差をつけよう!【動画編】
- ┠アコギで弾こう!ブルースギター【動画編】
- ┠のりのりFUNKYリズムギター【動画編】
- ┠カントリー&ロカビリー【動画編】
- ┠いまどき ソロアコギ【動画編】
- ┗アドリブ入門【動画編】
- レビュー & 豆知識
- ┠試奏の流儀
- ┠ギターよもやま話
- ┠動画でレビュー!! J-Guitar試奏室
- ┗アコギ エレアコ化計画
- コラム
- ┠ソロ・ウクレレ、いかがでしょう?
- ┗大友博の音楽旅コラム
< アーカイブ >
- 初心者向け
- ┗ギターはじめの一歩
- 初心者/中級者向け
- ┠フレットで覚える音楽の仕組み
- ┠スライドギター天国
- ┗アコースティック ソロギター道場
ギターテクニック 記事一覧
- 初心者向け
- ┠【ギター選びから!】ゼロから始めるギター
- ┠ギターはじめの一歩【動画編】
- ┗ウクレレを弾こう
- 初/中級者向け
- ┠ギター好きも楽しめる、ソロ・ウクレレ講座
- ┠ルーツへ帰ろう!!<復刻版>
- ┠ルーツへ帰ろう!!【動画編】
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?<復刻版>
- ┠ナイロン弦ギターはいかが?【動画編】
- ┠ドレミでアドリブ 簡単攻略法【動画編】
- ┠アコギで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┠エレキで弾こう!スライドギター【動画編】
- ┗イマドキ ロックギター入門【動画編】
- 中級者/上級者向け
- ┠ジャジーなソロアコギ
- ┠アコギ定番フレーズをサクッとトライ!
- ┠ワンランクアップのためのアコギ術
- ┠ワンランクアップのためのエレキ術
- ┠ソロギターをもっと楽しく!アコギ・アレンジ講座
- ┠高みへ挑戦!トミー・エマニュエル・スタイル
- ┠セッションマスターへの道【動画編】
- ┠アイリッシュギターを嗜もう<復刻版>
- ┠アイリッシュギターを嗜もう【動画編】
- ┠アコースティック ソロギター道場【動画編】
- ┠ソロアコギ・アレンジ講座【動画編】
- ┠ジャジーなギターで差をつけよう!【動画編】
- ┠アコギで弾こう!ブルースギター【動画編】
- ┠のりのりFUNKYリズムギター【動画編】
- ┠カントリー&ロカビリー【動画編】
- ┠いまどき ソロアコギ【動画編】
- ┗アドリブ入門【動画編】
- レビュー & 豆知識
- ┠試奏の流儀
- ┠ギターよもやま話
- ┠動画でレビュー!! J-Guitar試奏室
- ┗アコギ エレアコ化計画
- コラム
- ┠ソロ・ウクレレ、いかがでしょう?
- ┗大友博の音楽旅コラム
< アーカイブ >
- 初心者向け
- ┗ギターはじめの一歩
- 初心者/中級者向け
- ┠フレットで覚える音楽の仕組み
- ┠スライドギター天国
- ┗アコースティック ソロギター道場